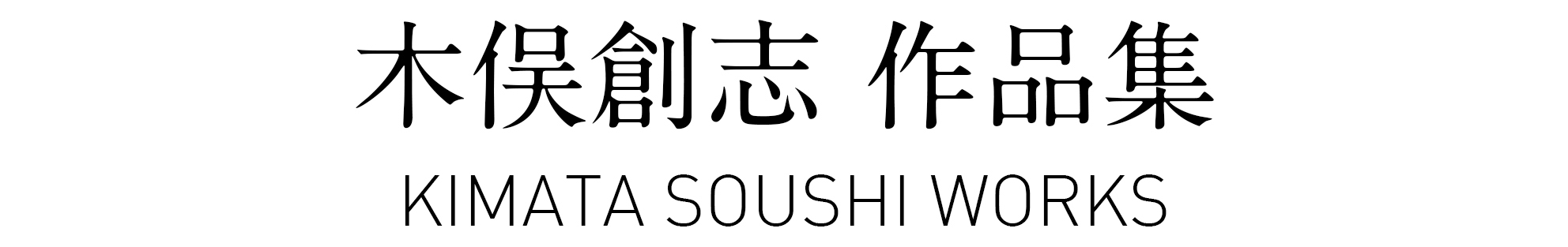最後まで読んでくださった方へ
私は子どもの頃から絵を見るのが好きだった。10代始めに油絵をかき始めたが、絵をかくのと同じくらい見るのが好きで、学生時代は3日に1回くらいのペースで展覧会に足を運んでいた。そんな中でセザンヌは常に別格だった。
セザンヌの絵は、彼がキャンヴァスに投じた最初の1本のストロークが、あたかも、ひと粒の種子となって、画面全体の成長を促し有機的に繋がり、こちらに向かって立ち上がる植物を見るかの様な感覚を私に及ぼした。
一本の筆跡、その物質としての絵の具の輝きは、味わい深く私の視界に木魂していた。彼の絵を見るというのは、ひと夏の植物の成長を見守る季節を追体験するかの様でもあり、また私自身が1枚の絵を仕上げる時間を追体験するかの様でもあった。
ひと夏の植物の成長、それは無垢な赤子が世界に眼差しを投げかけたときの、世界が立ち上がるプロセスに他ならない、ということにも薄々気づいてきた。
モネは目に過ぎない、しかし、なんという目だろう!
Ce Monet, ce n’est qu’un oeil, mais quel oeil !
セザンヌの絵を見るたびに、彼のフォルマリスティックな姿勢の背後にあるものを、今いちど凝視する必要を感じてきた。彼が残したとされる言葉には、20世紀に開花するフォーマリズムへの深い懐疑をすでに予告していたとさえ思わせるものがある。
また、彼の言葉と従来のセザンヌ観とが結節点を見出しにくい理由は、その点にこそあるのではないかと私は考えてきた。一般に言われているように、セザンヌがもし生粋の即物主義者、フォルマリストであるならば、どうしても解決できないセザンヌが私の眼前に出現していたからだ。
唐突ではあるが、こうした考えは、前世紀の指揮者ウィルヘルム・フルトヴェングラーの演奏に接しているときに突如鮮明になった。というのも、独断ではあるが、彼の、-曲の全体観を把握する類まれな構成に常に認められる- 硬直したところが微塵もない再現こそ、まさしくセザンヌの望んでいたものだと思われたからだ。
“楽譜に忠実”でありさえすればよいとされるフォーマルで即物的(ノイエザハリヒカイト 独Neue Sachlichkeit)なスタイルではなく、楽譜の深奥へ“能動的に”迫ってゆくフルトヴェングラーの耳の構造は、揺るぎない形式の中に常に空間の歪みや軋み、亀裂、破綻といった要素が認められるセザンヌの眼の構造とどこか似ている様に思われた。つまりセザンヌにとっての空間の歪みは、フルトヴェングラーにとってのテンポの揺れと同質のものなのだ。
ハインリヒ・シェンカーによる「遠聴」(独Fernhören 今聞こえている音の彼方に音を聞こうとする)理論のもと演奏するフルトヴェングラーの姿勢、そして、常に視界の彼方へと眼差しを注いでゆこうとするセザンヌの「能動的な眼線」には、再現者としての共通の哲学が認められるのであり、そう考えなければ、ヴィクトワール山や水浴図がモティーフとなった理由が私には判らなかった。
無論、即物主義的指向はセザンヌがその先駆と見做されてきたのかもしれないが、その方向を突き詰めていった果てに、「語り」や文学的内容と呼ばれてきたものが顕現するかしないのか。
また逆に、人間が“能動的に”見ることを突き詰めた果てに、そこに果たして本当に絵画としての価値が顕現するのかしないのか。一見相異なるかのように見えるふたつのベクトルのギリギリの戦い、その戦場が、彼の絵の本質ではないかという考えはそうした発想から生まれた。
絵というのは、そもそもものも言わず動きもせず、展覧会場には画家がいない場合も多く、例えば映画やコンサートなどと異なり、いたって働きかけの少ないメディアである。
であればこそ、逆に一たび自身の感覚にフィットした作品に出合った場合には、グイグイとこちらに向かって働きかけ、-ということはつまり、こちらが絵に向かってグイグイ働きかけ- 様々な推測や憶測を楽しめる場合が多い。とくに自分の関心の的になったのが、理屈抜きで自身のこころを感動させる作品たちだ。
小洒落たインテリア風アート、技巧を凝らした作品、資料的価値ある作品などより、不器用でもよいからダイレクトにこころを鷲掴みにする作品。むしろ“不器用さを武器”に自分の言いたいことのみに真っ直ぐな作品。そして、なぜ自分はこの作品に感動しているのかということを考えさせる作品。そんな絵がとても好きだった。
本エッセイ『セザンヌは自然をこう視た』は、そうした自身の性癖、分析癖が元になっており、私自身の独断的なセザンヌ像を明確にすることを目的に、彼について書き留めた雑多なメモを気の向くままに羅列したものである。
私が学生だった頃、「セザンヌが判らん」という友人に何人も出会い、彼らの恥を怖れぬ正直さに感心するとともに、セザンヌ好きの私は「“好み”とはそんなものか…」と驚かされた。そうした記憶も本エッセイをまとめる動機となった。
この度これをまとめるにあたり、常により困難な方へ -より高みへ- と自身を追い込んでゆくセザンヌが、私はあらためて好きになった。
おそらく、言葉でクリアにしていけばゆくほどクリアにできないもの、あるいは、言葉の空隙に存在するものがアートなのだろう。
本エッセイを最後まで読んで下さった方には、こころよりお礼申し上げる。
名作は、常に一義的な解釈を越えた様々な想いを受け手に与え、セザンヌの、こと最晩年の作品も、勿論そうした名作に数えられるべきものである。本エッセイを読み進み、おしまいの方に近づくにつれ、にわかには賛同できない部分が散見したかもしれないが、その賛否は読者ひとり一人に委ねたい。
セザンヌの研究書は概論の類しか把握していないことを告白するが、メルロー=ポンティ『眼と精神』だけはかつて興味深く読み進めた。この書からは多くを学んだ気がする。
ポール・セザンヌからもらった大いなる感動へのささやかなオマージュとして、本エッセイが新たなセザンヌ・ファンを生み出すことを願ってやみません。