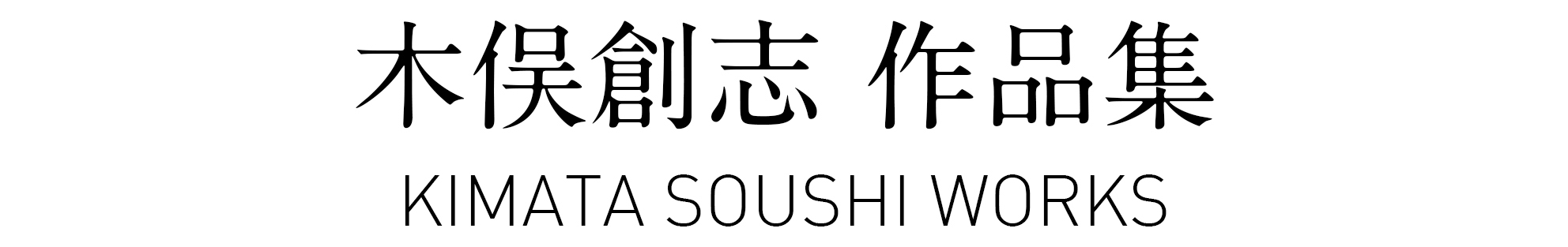おそらく彼は、ヴィクトワール山シリーズで、その分厚い奥行きを通じ「大自然」「宇宙」あるいは「この世」を描こうとした。しかし、どんなに筆を走らせても、眼前に拡がる世界が、自身の視界から遠ざかってゆくような感覚をおぼえたのではないか。ヴィクトワール山が、遥か遠くに、描けば描くほど掴み切れないもどかしさを常に感じながら。
一方、それとは逆に、肖像画シリーズで描こうとしたものは「個としての存在」「小さな存在」「限りある命」だったはずが、そこでも彼は、あるいは同じような事態に直面してしまったのかもしれない。
水浴図には、その両方が -「自然と人間」が登場する。
彼の水浴図は、「能動的な眼線」があてどなく彷徨った末の、まるで行き場を失った終着点であるかのような印象を与える。
言い換えれば、自然すなわちヴィクトワール山(=大自然、宇宙、世界)と、肖像画(=個としての小さな存在、小宇宙、人間)とを、突き詰めた果ての両者の架け橋とでも言えばよいのか。
観察を通しての感覚(サンサシオン sensation仏)の実現、その重要性を繰り返し述べてきたセザンヌではあるが、にもかかわらず、水浴図は彼の代表作中、奇しくもフィクションだ。
晩年には、あのルノワールと浅からぬ親交があったとも言われているが、そんなルノワールとは真逆の、水浴図の無表情な裸像たちにみる非情な肉の塊。
人間の裸がいびつに折り重なり“物化”する様相は、さながら20世紀の物質主義、さらには、(同じ世紀に生きてきた僕たちが最も鮮烈なイメージとして網膜に焼き付けている)ホロコーストの図さえ予視しているかのようにみえる。
モデルを雇う経済的な余裕がありながら、こと『大水浴図』シリーズの制作でそれをしなかったのは何故か? 視覚と絵画の問題を、生涯、制作を通じ考え続けてきた画家にとって、「モデルを前にするのが不快」との理由 -これはしばしば語られるが- で済ませることは出来ない。
唐突ではあるが、生身の人間が眼差しを注がれるときに覚える感覚とは、どういうものか?
眼差しを注がれた人間がオブジェと化し、自由を拘束され、まさしく“物化”していくその構造を初めて鮮明にしたのは、前世紀半ばサルトルだった。彼の念頭にあったものが、同時代を生きた過酷なホロコーストのもとで自由を奪われた人々であったのか、あるいはメドゥーサの神話であったのか…
いずれにしても、美術の基礎訓練において、生身のモデルをいちどは“物”として観察しなければならない、そんな画学生の“通過儀礼”と相俟って、彼の「眼差し=物化」理論は、学生時代の自分の脳裏に深く鮮烈に刻まれた。
だが、そんなサルトルより遥か以前に、愚直なセザンヌは「見る・見られる」に内在するその構造を直観したのかもしれない。
そう、彼は“物化”を避けたかったのだ!
セザンヌの水浴図は「視覚的な問題」からも解放された、彼の祈りにも似たイメージの産物に他ならないのである!