以前僕は、こんなことを話した。
セザンヌの絵から感じられる「躍動する部分」、それはまるで、絵全体を壊しかねないほど生動し、画面全体を生き物のように立ち上げてこちらに歩み寄ってくる原動力となっているのだ、と。
しかし一方で、その躍動をギリギリのところでガッチリ押さえ込んでいる「堅固な全体感」の存在。こうして、「部分」的でもあり「全体」的でもある絵画が実現し、それはあたかも褶曲する地層のように -身じろぎせずじっと重圧に耐えるかのような- 引き絞られた力を無言で放射しつづける、そんな緊張感となって僕たちを魅了する原因になっているのだ、と。

『風景』と題された作品をとりあげて、そんな話に始まり、『リンゴとオレンジ』では「安定感」と「不安定感」。『赤いベストの少年』では「平面性」と「空間性(奥行き)」などといった切り口で、そして、ヴィクトワール山シリーズでは、「抽象」と「具象」、さらに「均質」性と「スポット」性といった切り口も加わり、彼の絵の「アンビヴァレントな感覚」の達成ぶりを、つまり“相反するエレメントの拮抗”、反対感情の両立といった、その巨大な振幅ぶりを考えてきた。
要するに彼の絵は、どのように切ってみても、“孤独だが寂しくない”とか“長かったけれど、あっという間だった”とか“泣きながら喜んでいる”、みたいなことがみてとれるのだ。
「20世紀美術の父」と評されることの多いセザンヌではあるが、これまで述べてきたこうした彼の特徴は、どちらかと言えば、20世紀の美術、現代アートが苦手としてきたスタイルかもしれない。
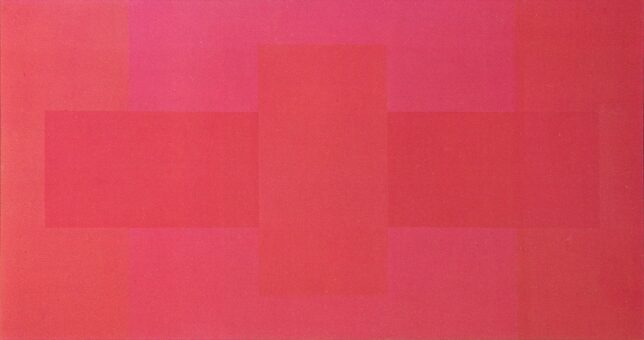
というのも、大雑把に言って、20世紀の美術、現代アートは、(セザンヌのしたように)ある種の全体感やバランス感覚にもとづいて対極にある要素の拮抗とそこから生じる緊張感を楽しむというような方法より、あるひとつの要素を純粋化ないし極大化していくことで -例えば、色だけが唯美しいとか、画面がとことん重たいとか、内容が徹底して“無意識の世界”である、あるいは(上の絵のように)作品が徹底して物質的である、といった具合に- 作品としての価値を明確にし強固にしていくという方法を重んじてきたからだ。
とすれば、彼が「20世紀美術の父」、「現代美術の産みの親」と呼ばれるとは何というパラドクスか。
